『Monster Hunter Wilds』は、シリーズ最新作として多くの期待を集めながらも、その方向性に疑問を抱かせる作品となってしまった。過剰なグローバル配慮や初心者優遇によって、従来の“狩猟”の緊張感や達成感が薄れ、モンハン本来の魅力が損なわれていると感じたベテランプレイヤーは少なくない。本記事では、筆者自身のプレイ経験を交えながら、『ワイルズ』における“モンハンらしさ”の喪失について考察していく。
広告

まず初めに、筆者のハンター歴について簡単にご紹介しておきたい。ワイルズのプレイ時間は260時間、HRは400以上。勲章コンプリート済みで、シリーズについては初代Monster Hunterからすべてのコンシューマー作品をプレイしてきた(フロンティアは除く)。武器は一貫してハンマーを愛用してきたが、残念ながら今作『Monster Hunter Wilds』では、そのハンマーが事実上“殺された”ので、いろいろな武器を使って狩りを楽しんでいる。
“ボリューム不足”という声の真意とは
『モンハンワイルズ』に対してよく聞かれる批判の一つに「ボリューム不足」というものがある。しかし実際のところ、本当にそうだろうか?

例えば、初期登場モンスター数を過去作『モンスターハンターワールド』と比較すると、ワールドが30体、ワイルズが29体と、数自体にはほとんど差がない(現在は30体)。釣りや環境生物の要素も引き継がれており、見た目の項目数や機能の“実装そのもの”においては決して劣っているわけではない。
ではなぜ、ワイルズは「ボリューム不足」と感じられてしまうのか?
最大の要因は、素材入手の難易度が極端に緩和されたことにある。ワイルズは海外展開を意識して制作されているが、Redditなどの海外フォーラムではモンハンシリーズに対して「素材を集めるのが面倒」「お金で装備を買えるようにしてほしい」といった意見が長年投稿されており、ワイルズではこうした声に対して妥協的な対応がとられたように感じる。例えば、傷をつけたり部位を破壊するだけで素材が入手できたり、調査クエストで確定報酬として宝玉や逆鱗が手に入る仕様などは、間違いなく素材集めのハードルを大きく下げている。
その結果、「素材を集めるために何度も狩りを繰り返す」というモンハン特有のサイクルが弱まり、「狩る目的」そのものが希薄になってしまっているのだ。

また、ストーリークリア後は主に歴戦の個体を狩猟することで手に入る素材を用いて、強力な武器を生成するアーティア武器という要素が用意されているわけだが、このアーティア素材を効率的に手に入れるためには現状歴戦アルシュベルド or 数種類の歴戦モンスターを含む多頭クエストしか選択肢がない、ということも、この「狩る目的」の希薄化に拍車をかけているように思う。
また、達成感に関しても大きな問題がある。勲章集め、環境生物の収集、魚釣りなど、過去作ではクリア後のやり込み要素として十分に機能していたコンテンツが、今作ではほぼ“報酬なし”の状態にある。例えば、環境生物を集めてもテントに飾る機能がなく、達成に対するご褒美や見返りがない。チャームや見た目装備などを用意することも可能だったはずだが、それらは実装されていない。前作で存在したものを“代替案なしに”削除するというのは、単なる怠慢としか言いようがない。

さらに、やり込み要素として多くのプレイヤーが楽しんでいた「闘技大会クエスト」も、発売から3ヶ月が経過しているにもかかわらず、チャタカブラとリオレイアの2体分しか用意されていない。全29種のモンスターのうち、たった2種というのは、やる気があるのか疑わざるを得ないレベルだ。

細部の作り込みに関しても粗が目立つ。例えばアーティア武器に関しては、所有武器のお気に入り登録機能がない、武器リストにソートや並び替えができない、全てのアーティア武器の見た目が一緒であるにもかかわらず武器の着せ替えができない──など、ユーザー視点の不在を感じさせる仕様が散見される。メニューの挙動に関しても、「メンバーリストを開いてプロフィールを確認した後、なぜかメニューが閉じられてしまい、再び開き直す必要がある」など、UI/UX面でも明らかに洗練されていない。
やり込めばやり込むほど不便が目立ち、ストレスが溜まっていく──それが今作に対する「ボリューム不足」という印象を強めているのではないだろうか。
頼もしさを増したオトモアイルーと、粗の目立つセクレト
「MHP 2nd G」から長きにわたりシリーズを支えてきたオトモアイルーは、今作『ワイルズ』でさらなる進化を遂げた。サポート行動は大幅に強化され、並のハンターよりも活躍する場面すら見られる。一方で、オトモアイルーがサポート行動の「ネコ式火竜艇」を行っている際に、うっかりハンターが力尽きてしまい、同じくサポート行動の「ミツムシど根性」が発動してしまうと、オトモアイルーが援護射撃を止めずになかなか蘇生してくれない、という不可解な挙動も見られるが、全体としては非常に頼もしい存在だと言える。
対照的に、今作で新たに登場したセクレトに関しては、問題点が多く指摘されている。前作『ライズ』のオトモガルグのような戦闘サポート能力は一切なく、戦闘中は離れた位置で突っ立っているだけ。それどころか、その立ち位置が絶妙に邪魔で、カメラや攻撃の邪魔になる場面も珍しくない。
「態勢立て直し」も新たな戦術ツールとして期待されていたが、実際には呼び出した瞬間にモンスターの攻撃に突っ込んでしまい、ハンターごと巻き込まれて力尽きるというシーンも多々見受けられる。これは明らかに挙動の設計ミスと言わざるを得ない。
とはいえ、セクレト騎乗中のオート移動やアイテム使用といった利便性の高さは一定の評価に値する。ポテンシャル自体は十分にあるため、今後のアップデートによる改善に期待したいところだ。
ワイルズが見せた“進化”──評価すべきポイントもある
ここまで批判的な視点を中心に語ってきたが、『モンハンワイルズ』にも称賛すべき点は多い。まず注目すべきは、戦闘アクションの爽快感だ。今作の目玉とも言える「傷+集中弱点攻撃システム」は、プレイヤーに新たな戦略性と選択肢を与えており、シリーズの中でも屈指の爽快感を実現している。さらに、「相殺」や「鍔迫り合い」の導入により、従来の“ターン制バトル”的な戦闘スタイルから脱却し、敵の攻撃ターンに割り込んで反撃できるようになったことで、狩りのアクション性と緊張感が格段に増した。
グラフィック面も特筆に値する。超重量級のグラフィックは、次世代機ならではの美麗な表現を実現しており、フィールドの臨場感やモンスターの存在感に大きく寄与している。これに対し、一部からは「重すぎる」との声も上がっているが、その多くは旧世代スペックのPCユーザーによるものであり、これはゲームのせいではなく、自身の環境に問題があると言わざるを得ない。これを機に新しいPCを購入するか、PS5 Proの導入を検討してほしいところだ。
また、全武器種のバランスについても一考に値する。残念ながら筆者が長年愛用してきたハンマーに関しては、「傷システム」との相性の悪さからシリーズ最低評価と感じているが、それ以外の武器は比較的良好なバランスに調整されているように思う。今作では複数の武器を試しているが、それぞれに明確な個性とコンボの魅力があり、ある程度練習すればどの武器でも強力な立ち回りが可能になる。これは武器選択の幅を広げる上で、素晴らしい進化の一つだ。
こういった素晴らしい進化があるだけに、余計に粗が目立つ形になってしまうように思う。
広告
失われた“狩猟”の本質──モンハンはどこへ向かうのか
『ワイルズ』は確かに美しいグラフィックやスムーズな操作性など、技術的には進化している。しかし、その裏でモンハンシリーズが築いてきた「狩猟」というアイデンティティが薄れていることに、多くのベテランハンターが気づいているはずだ。
これが一時的な方向転換であれば良いが、もしも今後この路線が「スタンダード」となるのであれば、かつての「狩りに挑む緊張感」を愛していたユーザーは離れていくことになるだろう。
結論:迎合ではなく、「信念」を貫く作品を

モンハンという作品がここまで支持されてきたのは、単に売れるゲームだったからではない。開発陣の“狩猟という体験”へのこだわりと、それに真摯に向き合うプレイヤーたちの存在があったからだ。
『Monster Hunter Wilds』が示した方向性に、賛否が分かれるのは当然だろう。しかし今こそ、シリーズが築き上げた“魂”を再確認し、迎合ではなく“信念”をもって作品を作り続けてほしい──そう強く願う。


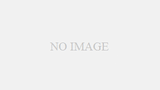
コメント